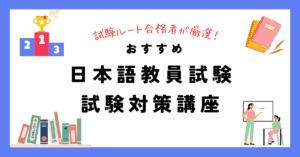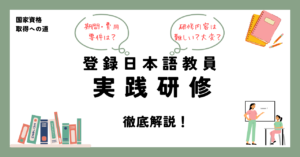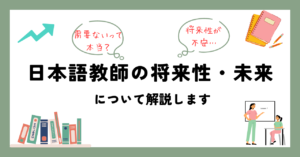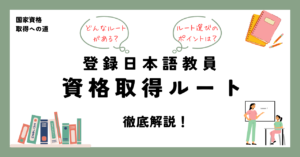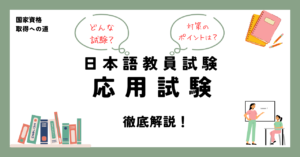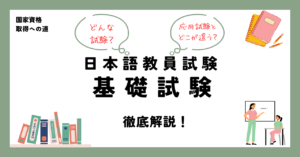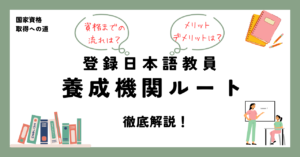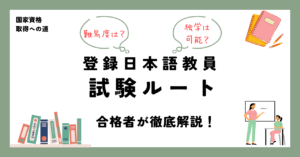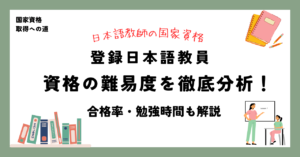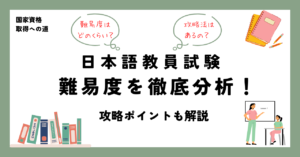\ おすすめスクールはこちら /
TCJ日本語教師養成講座 | ・併設日本語学校で現場を体験 ・バランス重視のカリキュラム ・国家試験対策も充実 |
ヒューマンアカデミー | ・全国主要都市をカバー ・柔軟性の高い受講プラン ・最大手の安心とサポート内容 |
KEC日本語学院 | ・関西を拠点に6校舎を展開 ・実践重視のカリキュラム ・少人数制で実践力を養成 |
この記事では、日本語教育機関認定法の施行によって新設された「登録日本語教員養成機関」について詳しく解説します。
法律に基づく認定を受けて養成課程を実施できる登録日本語教員養成機関の登録が始まりました。
日本語教師志望者は、登録日本語教員養成機関における養成課程で学び、修了することで、さまざまなメリットを受けられます。
- 登録日本語教員養成機関って何?
- 従来の養成講座と何が違うの?
- 登録日本語教員養成機関で学ぶメリットは?
- 登録日本語教員養成機関はどこにある?
まだまだ数の少ない登録日本語教員養成機関。
あえて選択する必要性がどのくらいあるのでしょうか。
この記事では、これから登録日本語教員をめざす方のために、制度の概要、メリット、従来の養成講座との違いなど、登録日本語教員養成機関に関して詳しく解説します。
当サイトのおすすめ日本語教師養成講座No.2
\ 口コミ評価 (4.5) /
ヒューマンアカデミー

<全国32校舎・業界最大手の安心感!>
<国家資格対応・日本語教員試験基礎試験免除>
<日本語教員試験合格率91.8%!>
<実習・サポートも充実! 就職率96.3%>
<リスキリング支援制度で最大70%還元>
<教育訓練給付金制度で最大50%おトクに!>
\ まずは気軽に相談、オンラインもOK/
登録日本語教員養成機関とは?
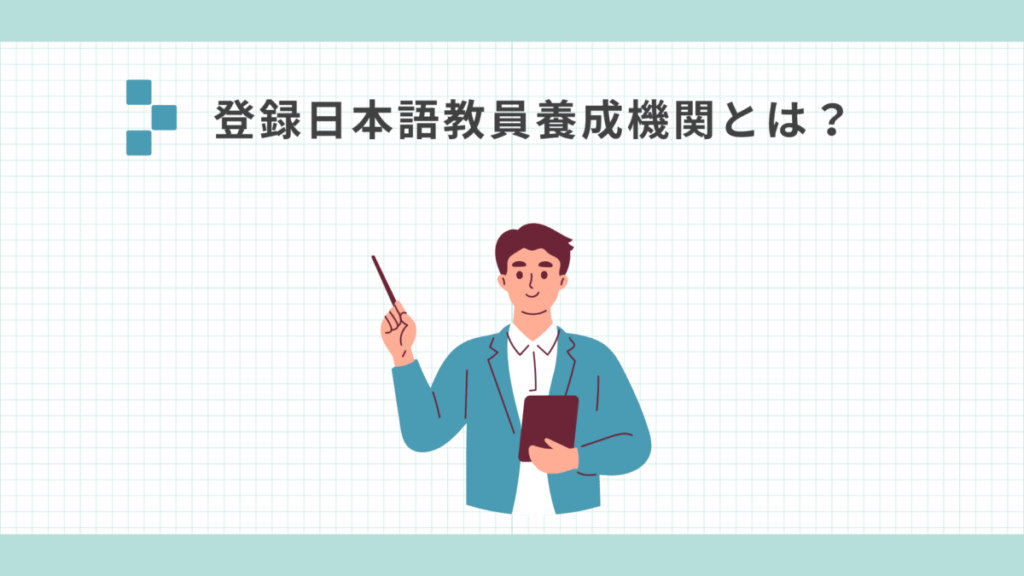
登録日本語教員機関とは、日本語教育機関認定法に基づき、国が認定した日本語教師養成機関のことです。
法律による認定を受けていることが、一般の日本語教師養成講座と異なります。
登録日本語教員養成機関で学ぶことで、プロの日本語教師になるための専門的なスキルを身につけられます。
また、国家資格(登録日本語教員)を得るためのメインルートにも位置付けられています。
日本語教師としてのスキル習得と国家資格取得を同時にめざすことができるのが、登録日本語教員養成機関です。
登録日本語教員養成機関には2種類ある!?
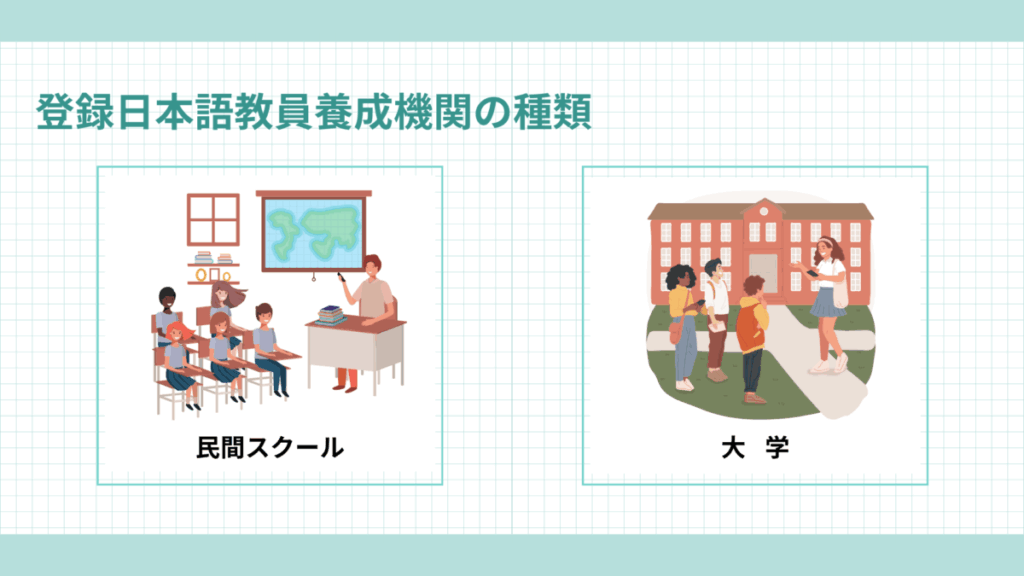
登録日本語教員養成機関には、大きく2種類のタイプがあります。
- 民間スクールの日本語教師養成講座
- 大学(大学院)の日本語教員養成課程
どちらも登録日本語教員養成機関ではありますが、異なる点があるので、それぞれ解説します。
1 民間スクールの日本語教師養成講座
民間の日本語学校や資格スクールが運営する日本語教師養成講座で、登録日本語教員養成機関として認められたものがこれにあたります。
おおまかな講座設計や費用面については、従来の養成講座と大きな違いはありません。
授業の構成は、国が示すカリキュラムに基づく375単位時間以上。
多くの講座は教育実習を含んでおり、国家資格要件の実践研修(45単位時間以上)を含むカリキュラムが一般的です。
つまり、登録日本語教員養成機関の講座においても、420単位時間を満たす構成になっているわけです。
学歴・経験などを問わず受講可能なため、社会人から日本語教師をめざす方向けの養成機関です。
2 大学(大学院)の日本語教員養成課程
大学(大学院)のプログラムとして、登録日本語教員機関の認定を受けたものです。
基本的には、所属の学生対象のため、大学(大学院)への入学が必要です。
大学の養成課程には、
- 所定の学部学科の日本語教育学関連の主専攻(副専攻)
- 全学部生対象の養成プログラム
があり、大学によって異なります。
特定の学部生でないとプログラムへの登録ができない場合があるため、大学選びの際に注意が必要です。
養成課程修了に必要な単位数は25単位以上、実践研修修了に必要な単位数は1単位。
大学によっては、実践研修を実施していないところもあるため、国家資格を取得するには別途民間スクール等で実践研修を修了する必要があります。
登録日本語教員養成機関で学ぶメリットとは?

日本語教員試験の基礎試験が免除される
登録日本語教員養成機関の養成課程を修了した場合、日本語教員試験の基礎試験の受験が免除されます。
このため、日本教員試験の応用試験さえ合格できれば、実践研修を経て国家資格が取得できます。
基礎試験は合格率が10%以下と非常に難易度が高い試験です。
登録日本語教員養成機関で学び、基礎試験免除の権利を得ることで、国家資格取得への道が近くなります。
学士の学歴がなくても国家資格要件が満たせる
一般の養成講座を修了する「経過措置ルート」では学士(四大卒)以上の学歴が必要です。
しかし、登録日本語教員養成機関を経る「養成機関ルート」では学歴要件はありません。
登録日本語教員養成機関での養成課程を修了することで、大卒の学歴がなくても、国家資格要件を満たすことができます。
新制度に準拠したカリキュラムで学べる
登録日本語教員機関の養成課程は新たな国家資格制度に基づき、文部科学省による認可を受けたカリキュラムで行われます。
最新のカリキュラムで学ぶことで、日本語教師として今求められている知識・スキルを身につけられます。
また、修了すると、法令に基づく様式で修了証が交付されます。
登録日本語教員養成機関を修了することで、日本語教育を行うために必要な知識・技能を習得していることを客観的に証明することができます。
登録日本語教員養成機関の養成課程のカリキュラムは?
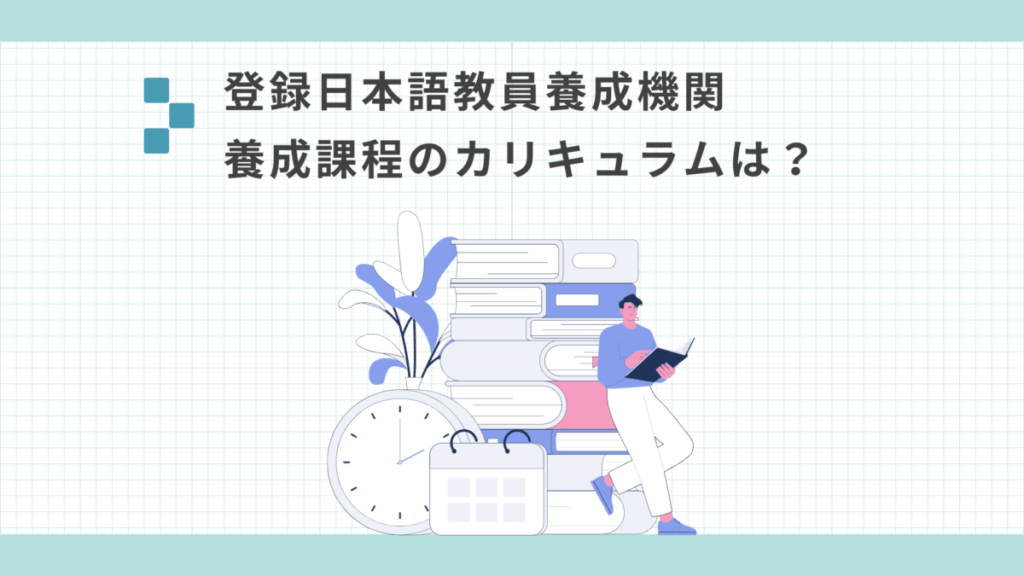
カリキュラムは国が新たに策定した「登録日本語教員 実践研修・養成課程コアカリキュラム」(以下「コアカリキュラム」)に基づいて作成されます。
内容としては、基本的に、平成31年の「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版」における「必須の教育内容」を踏襲。
登録日本語教員養成機関の大まかなカリキュラムは、従来の文化庁届出受理講座とはそれほど変わりません。
ただし、コアカリキュラムでは、さらに具体的な内容(目標)が追加されています。
コアカリキュラムは、以下2つで構成されています。
▼各コアカリキュラムの構成▼
コアカリキュラム
コアカリキュラム
特徴的なのは「到達目標」で、「何ができるか(Can-Do)」が具体的に記載されています。
近年の日本語教育のベースとなっている「日本語教育の参照枠」を意識しているようです。
このように、コアカリキュラムには養成段階で身につけておくべきスキルが具体的に示されています。
日本語教師をめざす方には定期的に目を通すことをおすすめします。
登録日本語教員養成機関と文化庁届出受理講座の違いは?
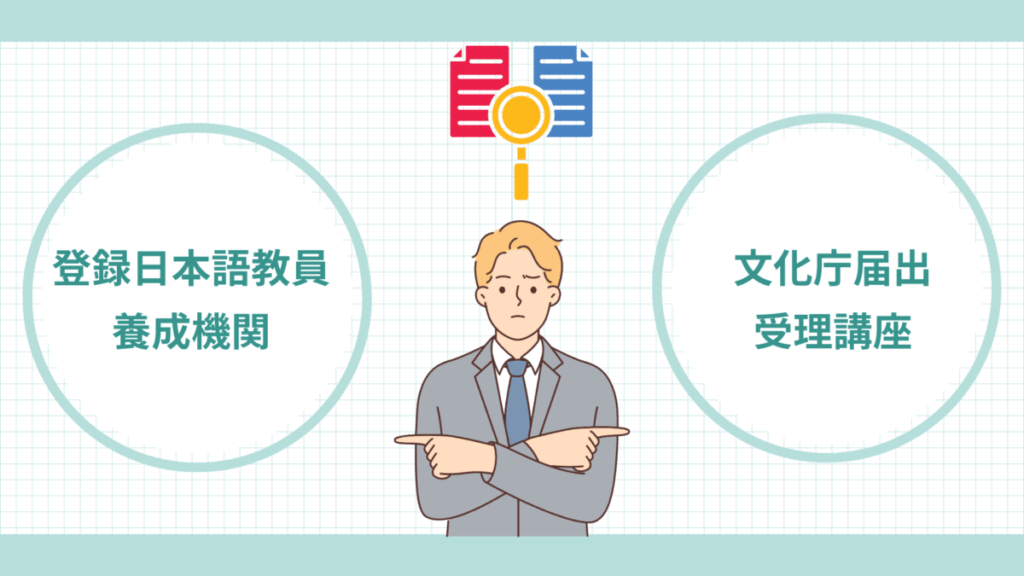
新設された登録日本語教員養成機関は、従来の養成講座(文化庁届出受理講座)と何が違うのでしょうか。
実は、講座のカリキュラムや学習内容は、ほぼ同じです。
どちらも平成31年に国が示した「必須の教育内容」に基づいたカリキュラムのためです。
しかし、制度面では無視できない違いが見られます。
▼登録日本語教育機関と従来との比較▼
| 登録日本語教員養成機関 | 文化庁届出受理講座 | |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 日本語教育機関認定法 | 法務省告示基準 |
| 審査機関 | 文部科学省 | 文化庁 |
| 資格取得ルート | 養成機関ルート | Cルート |
| 単位時間数 | 375単位時間 ※実践研修(45単位)を加えて420単位時間 | 420単位時間 |
| カリキュラム | 必須の教育内容 | 必須の教育内容 |
| 教育訓練給付金 | 特定一般教育訓練給付金 | 一般教育訓練給付金 |
制度面の違いと受講生への影響について、3つのポイントから解説します。
法令上の取扱いが違う
登録日本語教員養成機関と文化庁届出受理講座は、根拠となる法令上の取扱いが異なります。
文化庁届出受理講座は2024年3月まで、国が求める基準を満たす日本語教師養成講座として指定された講座です。
2024年4月の日本語教育機関認定法施行後は、文化庁届出受理講座の新規認定は終了。
新たに国家資格要件を満たす登録日本語教員養成機関の認定制度が始まりました。
これを受けて、認可の根拠法令は法務省告示基準から日本語教育機関認定法という法律になり、認可主体は文化庁から文部科学省へ。
国の認定審査は改めて行われることとなり、法令上の取扱いにおいて事実上格上げされたと考えられます。
国家資格取得ルートの違い
登録日本語教員養成機関の場合は「養成機関ルート」、文化庁届出受理講座の場合は「Cルート」になります。
どちらのルートも、日本語教員試験の応用試験に合格しなければならないのは同じです。
大きな違いは、学歴要件。
Cルートの場合は学士以上の学歴が必須の一方で、養成機関ルートは学歴不問です。
大卒以上の学歴がない場合、国家資格を取得するには、登録日本語教員養成機関を選択する必要があります。
教育訓練給付金の種別が違う
民間の養成講座を受講する場合、一定の要件を満たす求職者は、ハローワークから給付金を受け取ることができます。
指定講座の受講料の一部が還付される公的制度(教育訓練給付金)です。
教育訓練給付金には種類があり、従来の養成講座では「一般教育訓練給付金」として、給付の上限額は10万円でした。
一方で、登録日本語教員養成機関が実施する養成講座は「特定一般教育訓練給付金」として指定され、上限額は20万円に上昇。
講座修了後に就職要件を満たせば、さらに5万円上乗せされます。
よって、登録日本語教員養成機関による指定講座を受講するほうが、最大15万円多く給付が受けられます。
登録日本語教員養成機関の数はどのくらい?
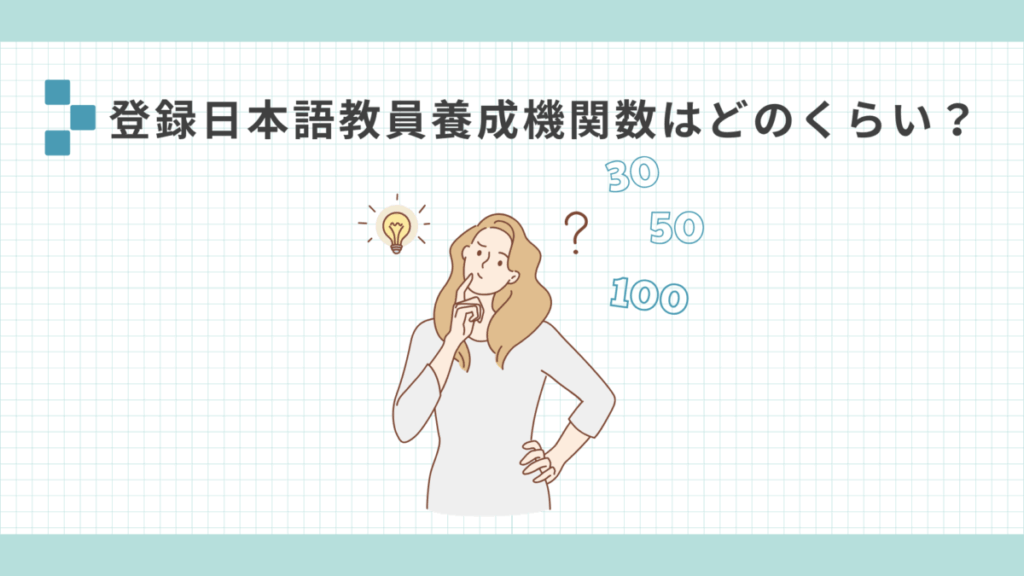
2025年4月時点の登録日本語教育機関数は、40です。
内訳は、
- 民間養成機関:16
- 大学(大学院):24
となっています。
新法施行時点で、文化庁届出受理講座が200機関以上認定されていたことを考えると、登録日本語教員養成機関の数は非常に少ないと言えます。
とはいえ、現状、多くの機関が登録申請に向けた手続きを進めているようです。
登録の機会が年2回しかないため急増は期待できませんが、今後増えていくことが予想されます。
登録日本語教員養成機関一覧
2025年11月時点で登録日本語教員養成機関として認定されている機関を一覧でご紹介します。
なお、最新の状況は、文部科学省ホームページで確認できます。
【登録日本語教員養成機関】民間スクール一覧
民間の養成スクールは31の機関が認定されています。
ただし、まだ開講していないスクールもあるため、開講時期など詳細は直接確認しましょう。
| スクール名 | 形式 | 費用(参考) | 所在地 |
|---|---|---|---|
| ヒューマンアカデミー | 通信 | 730,978円 | 全国主要都市 |
| TCJ日本語教師養成講座 | 通学/通信 | 646,000円 | 東京・大阪 |
| アルファ国際学院 | 通学/通信 | 742,420円 | 東京・横浜・名古屋・大阪・福岡・沖縄 |
| 千駄ヶ谷日本語教育研究所 | 通学/通信 | 622,000円 | 東京 |
| アークアカデミー | 通信 | 638,190円 | 東京 |
| インターカルト日本語教員 養成研究所 | 通信 | 638,000円 | 東京 |
| ルネサンス日本語学院 | 通信 | 556,103円 | 東京・横浜・名古屋・大阪 |
| 東洋言語学院 | 通信 | 585,000円 | 東京 |
| 東京明生日本語学院 | 通学 | 東京 | |
| 新宿日本語学校 | 通学/通信 | 570,000円 | 東京 |
| 文化外国語専門学校 | 東京 | ||
| リカレント新宿 | 通学/通信 | 594,000円 | 東京 |
| KCP日本語教師養成講座 | 東京 | ||
| SANKO日本語学校東京 | 東京 | ||
| 日本国際工科専門学校 | 千葉 | ||
| 船橋日本語学院 | 通学 | 千葉 | |
| 千葉モードビジネス専門学校 | 通学 | 千葉 | |
| 丸の内ビジネス専門学校 | 通学 | 長野 | |
| 静岡日本語学院 | 通学 | 静岡 | |
| 浜松日本語学院 | 通学 | 630,000円 | 浜松 |
| ECC日本語学院 | 通学 | 638,440円 | 名古屋 |
| 北國新聞文化センター | 金沢 | ||
| 京都民際日本語学校 | 通学 | 540,000円 | 京都 |
| 清風情報工科学院 | 通学 | 440,000円 | 大阪 |
| 国際交流センター | 通学 | 422,000円 | 大阪 |
| J国際学院 | 通学/通信 | 大阪・名古屋 | |
| 神戸東洋日本語学院 | 通学 | 550,000円 | 神戸 |
| 岡山外語学院 | 通信 | 岡山 | |
| 穴吹カレッジ キャリアアップスクール福山 | 通信 | 448,100円 | 広島 |
| 愛和外語学院 | 福岡 | ||
| 宮崎情報ビジネス専門学校 | 通信 | 594,000円 | 宮崎 |
※登録は法人単位のため機関数とスクール数は必ずしも一致しません。
【登録日本語教員養成機関】大学(大学院)一覧
大学(大学院)は60校が認定されています。
大学によって、全学部生を対象している場合と特定の学部・学科生しか履修できない場合があります。
履修要件をよく確認しましょう。
| 大学名 | 対象学部・学科 | 所在地 |
|---|---|---|
| 北星学園大学 | 文学部 | 北海道 |
| 青森大学 | 全学部 | 青森 |
| 国際教養大学専門職大学院 | グローバル・コミュニケーション実践研究科 | 秋田 |
| 東北大学 | 文学部人文社会学科 | 宮城 |
| 山形大学 | 全学部 | 山形 |
| 東日本国際大学 | 全学部 | 福島 |
| 筑波大学 | 人文・文化学群日本語・日本文化学類 | 茨城 |
| 筑波大学大学院 | 人文社会科学研究群 | 茨城 |
| 常磐大学 | 人間科学部 | 茨城 |
| 群馬県立女子大学 | 全学部 | 群馬 |
| 聖学院大学 | 人文学部日本文化学科 | 埼玉 |
| 麗澤大学 | 国際学部国際学科 | 千葉 |
| 麗澤大学大学院 | 言語教育研究科 | 千葉 |
| 明海大学 | 外国語学部日本語学科 | 千葉 |
| 和洋女子大学 | 人文学部日本文学文化学科など | 千葉 |
| 学習院大学 | 全学部 | 東京 |
| 白百合女子大学 | 全学部 | 東京 |
| 東京学芸大学 | 教育学部 | 東京 |
| 東洋大学 | 文学部/社会学部/国際学部 | 東京 |
| 目白大学 | 外国語学部日本語・日本語教育学科 | 東京 |
| 大妻女子大学 | 文学部 | 東京 |
| 武蔵野大学 | グローバル学部日本語コミュニケーション学科 | 東京 |
| 國學院大学 | 全学部 | 東京 |
| 成蹊大学 | 文学部日本文学科など | 東京 |
| 聖心女子大学 | 全学部 | 東京 |
| 文京学院大学 | 全学部 | 東京 |
| 関東学院大学 | 国際文化学部/文学研究科 | 神奈川 |
| フェリス女学院大学 | 全学部 | 神奈川 |
| 山梨英和大学 | 山梨 | |
| 常葉大学 | 外国語学部 | 静岡 |
| 椙山女学園大学 | 外国語学部/教育学部 | 愛知 |
| 愛知学院大学 | 文学部日本文化学科 | 愛知 |
| 金城学院大学 | 文学部日本語日本文化学科 | 愛知 |
| 京都産業大学 | 外国語学部アジア言語学科 | 京都 |
| 京都精華大学 | 国際文化学部グローバルスタディーズ学科 | 京都 |
| 京都ノートルダム女子大学 | 全学部 | 京都 |
| 京都外国語大学 | 外国語学部日本語学科 | 京都 |
| 京都橘大学 | 文学部日本語日本文学科など | 京都 |
| 京都光華女子大学 | 全学部 | 京都 |
| 同志社女子大学 | 全学部 | 京都 |
| 追手門学院大学 | 文学部人文学科/国際学部国際学科 | 大阪 |
| 関西外国語大学 | 外国語学部国際日本学科/英語国際学部アジア共創学科 | 大阪 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 大阪 |
| 神戸大学大学院 | 国際文化学研究科 | 兵庫 |
| 兵庫教育大学 | 学校教育学部 | 兵庫 |
| 神戸親和大学 | 全学部 | 兵庫 |
| 大手前大学 | 現代社会学部現代社会学科通信課程 | 兵庫 |
| 甲南大学 | 全学部 | 兵庫 |
| 関西国際大学 | グローバル学部 | 兵庫 |
| 岡山大学 | 全学部 | 岡山 |
| 山陽学園大学 | 総合人間学部言語文化学科 | 岡山 |
| ノートルダム清心女子大学 | 全学部 | 岡山 |
| 広島大学 | 教育学部第三類 | 広島 |
| 県立広島大学 | 地域創生学部地域創生学科 | 広島 |
| 広島文教大学 | 全学部 | 広島 |
| 比治山大学 | 現代文化学部言語文化学科 | 広島 |
| 香川大学 | 教育学部 | 香川 |
| 西南学院大学 | 外国語学部外国語学科 | 福岡 |
| 長崎外国語大学 | 全学部 | 長崎 |
| 熊本学園大学 | 全学部 | 熊本 |
当サイトのおすすめ日本語教師養成講座No.2
\ 口コミ評価 (4.5) /
ヒューマンアカデミー

<全国32校舎・業界最大手の安心感!>
<国家資格対応・日本語教員試験基礎試験免除>
<日本語教員試験合格率91.8%!>
<実習・サポートも充実! 就職率96.3%>
<リスキリング支援制度で最大70%還元>
<教育訓練給付金制度で最大50%おトクに!>
\ デジタルパンフレットを見てみる /
\ まずは気軽に相談、オンラインもOK/

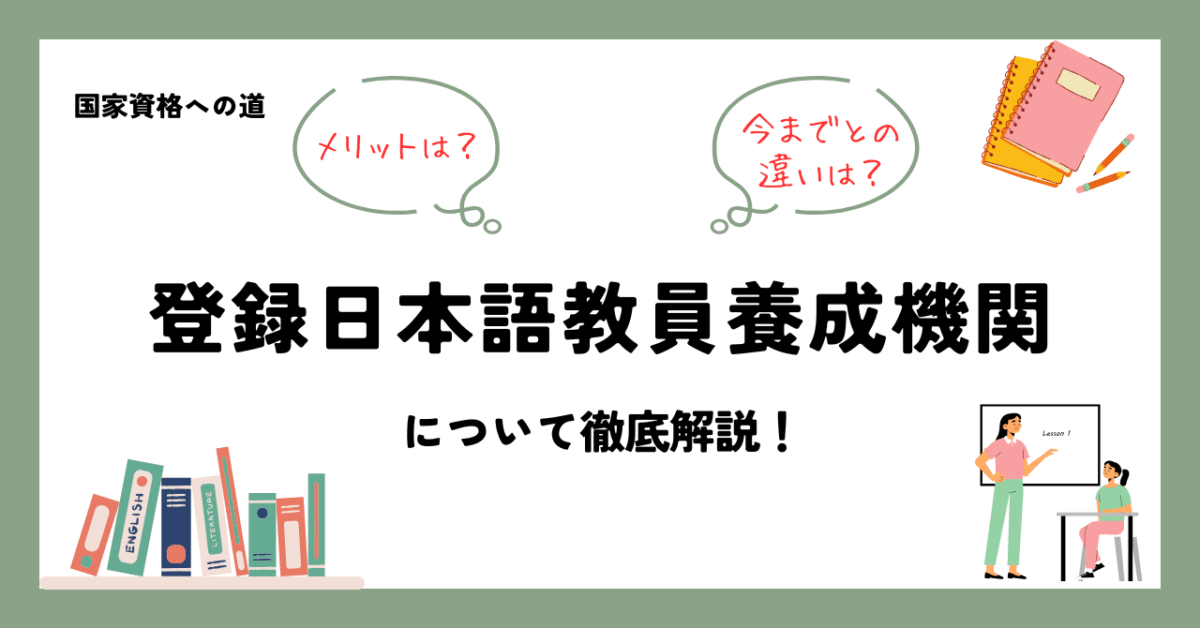


で取る方法-300x157.png)