国内日本語学校の求人情報を見ると、いくつかの採用要件の1つとしてこのような記載が必ずあります。
大学(大学院)で日本語教育を主専攻または副専攻し卒業していること
これは「留学」ビザのある外国人留学生を受け入れる日本語学校で働ける日本語教師の要件が国の基準によって定められているからです。
主専攻は45単位以上、副専攻は26単位以上の履修が必要です。
そこでこんな疑問が湧いてきませんか?
- 「主専攻」「副専攻」って何?
- 何が違うの?
- どっちがいいの?
こんな疑問を解消するためにこの記事では、大学で日本語教師の資格を取得するために知っておくべき「主専攻と副専攻の違い」について詳しく解説します。
・大学で日本語教師の資格を取りたいと思っている人
・「主専攻」「副専攻」の意味がよくわからない人
・日本語教育を「主専攻」にするか「副専攻」にするか迷っている人
当サイトのおすすめ日本語教師養成講座No.2
\ 口コミ評価 (4.5) /
ヒューマンアカデミー

<全国32校舎・業界最大手の安心感!>
<国家資格対応・日本語教員試験基礎試験免除>
<日本語教員試験合格率91.8%!>
<実習・サポートも充実! 就職率96.3%>
<リスキリング支援制度で最大70%還元>
<教育訓練給付金制度で最大50%おトクに!>
\ まずは気軽に相談、オンラインもOK/
大学の「1単位」ってどういう意味?
.png)
主専攻と副専攻の違いを理解するために、まずは大学の「単位」とは何かについて説明しましょう。
「単位」の概念は文部科学省大学設置基準で決まっていて、1単位は「45時間の学修を必要とする内容をもつて構成すること」(大学設置基準第21条第2項より抜粋)とされています。
「45時間」は授業だけでなく予習・復習の時間も含まれ、大学はこれに基づいてカリキュラムを構成しています。
一般的には、週1コマ(90分)の授業を半期で終える科目を履修すると2単位、年間科目は4単位取得できることになります。
大学卒業には、大学所定の124単位以上の取得が必要です。
では次に主専攻と副専攻について解説していきます。
「主専攻」と「副専攻」って何?

まず、「主専攻ってなに?」「副専攻ってなに?」という話です。
簡単に言ってしまえば、「主専攻」は専門、「副専攻」専門外 ということです。
もう少し詳しく解説します。
主専攻とは?
主専攻は学生が大学で一番深く研究する学問分野を専攻することです。
学位(卒業に必要な単位)を取得するために必要な主要な科目や単位を履修することが一般的です。
主専攻において、学生はその分野の基本的な理論やスキルを習得したうえで、専門分野におけるテーマを設定し、研究していきます。
主専攻で学んだ学問は、卒業後のキャリアプランに大きく影響してくる可能性も・・・。
よって、主専攻をどの分野にするかはしっかりとよく考えて選択する必要があります。
副専攻とは?
副専攻は主専攻以外の分野に関心を持ち、一定の授業や単位を取得することです。
専門の研究分野や教養の幅を広げるために学ぶイメージです。
主専攻とは違う学問領域に関する知識を習得して、幅広い知識やスキルを身につけることができます。
研究において学問領域を超えたアプローチをしていきたい場合に有効です。
また、将来の学問研究やキャリア形成において多彩な視点と可能性を見出すこともできるでしょう。
副専攻は大学独自の取組によるプログラムのため、副専攻にできる学部・学科や選択できる科目などのルールが大学ごとに異なり、事前の手続きや追加の学費が必要な大学もあります。
大学を決める際には志望大学のプログラム内容をよく確認しましょう。
日本語教師資格|「主専攻」と「副専攻」の違いは?
.png)
ここまでで主専攻と副専攻の意味はわかっていただけましたね。
次に日本語教師の資格取得をめざして主専攻・副専攻を選ぶとき、どのような違いがでてくるのでしょうか。
5つの観点からその違いを見ていきたいと思います。
①「必要単位数」が違う
日本語教師の資格を取得するのに、「主専攻は45単位以上」「副専攻は26単位以上」必要です。
副専攻は26単位とれば資格が取れるのに、主専攻は副専攻の倍近い単位数を取得しなければなりません。
単に「日本語教師の資格を取りたい」だけなら、取得する日本語教育の単位数は副専攻のほうが少なくて済みます。
ただし、単位数は国が定める最低基準のため、資格取得に必要な単位数は大学によって異なることに注意が必要です。
②「卒業要件になる単位数」が違う
大学卒業に必要な単位(卒業要件単位)数は124単位。
でも、在学中に取った単位すべてが124単位に認められるとは限りません。所属する学部学科と関係ない単位を124単位とっても卒業できるわけがないのはわかりますよね。
どんな科目の単位を卒業要件単位にできるかは、大学が一定のルールを作っています。このルールに沿って単位を取っていかないと卒業できないのです。
主専攻の場合ほぼすべての単位が卒業要件単位に含まれるのに対し、副専攻は一部しか認められないことが多いです。
つまり、副専攻で資格を取ろうとすると124単位以上の単位を余分に取らなければならないのです。
③「専門性の高さ」が違う
学ぶ科目数が多いので、当然ながら日本語教育に関する専門性の高さは主専攻のほうが上です。
知識の量だけではありません。
主専攻は日本語教育に関するテーマを研究し、卒業論文を書き上げることになります。
学習におけるインプット・アウトプット両面で主専攻のほうが専門性が高いのは明らかですね。
④「専門外知識の幅」が違う
日本語教育以外の知識の幅や量は副専攻のほうが多いです。
専門外の知識・研究が日本語教師になったときに役に立つことも結構あります。
例えば、日本語教師として学生の進路指導にあたるとき、自分の経験が役立つ場面があります。
日本語学校の学生の多くは日本の大学進学を目標にしています。
彼らは別に、日本の大学で日本語を研究したいのではありません(多少はいるかもしれませんが…)。
日本文学、経済学、経営学、社会学…理系の学部をめざす学生も…そんな学生を相手に自分の経験をもとにしたアドバイスができるでしょう。
このほか、自分の持つ専門知識を授業のネタにしても面白いかもしれませんね。
⑤「日本語教師としての実践力」が違う
主専攻と副専攻は取得単位数は違いますが、教育実習に必要な単位は1単位で同じです。
つまり、どちらも同じ内容の実習を経験します。
ただ、やはりバックグラウンドとなる知識の量が違うと、実践面でも表れてくるでしょう。
日本語文法、日本語教授法、言語学、第二言語習得論、教育心理学、対照言語学、コミュニケーション論、音声学・・・
日本語教育に活かせる学問分野は多岐にわたります。
より多くを学ぶ主専攻のほうが実践に活かせる知識の量が多く幅も広いのは間違いありません。
もちろん、習得した知識を実践に活かせなければ意味がないので、それは本人次第のところもありますが…
「主専攻」と「副専攻」|どっちが就職に有利?

主専攻でも副専攻でも所定の単位を取得して卒業すれば、同等の日本語教師資格を得られます。
でも、卒業後の進路のことを考えて、主専攻と副専攻のどっちを選べばいいのか迷いますよね。
卒業後日本語教育の世界に飛びこむことを決めているなら迷わず主専攻ですが、受験生や大学1・2年の段階では明確な進路が決まっていない学生も多いはず・・・
そこで、卒業後に考えられる3つの進路について、「主専攻・副専攻のどちらが就職に有利なのか」解説します。
・日本語教師として就職する場合
・日本語教育以外の一般企業に就職する場合
・研究者をめざして大学院に進学する場合
Ⅰ 日本語教師として就職する場合

主専攻のほうが有利に思えますが、採用試験で「主専攻」か「副専攻」かだけの点で有利・不利に働くことはありません。
日本語学校の求人情報で「主専攻はOKで副専攻はダメ」という採用要件は見たことがありません。
副専攻でも国の基準に基づくれっきとした資格だからです。
面接試験で「大学で何を学んだか」と「日本語教育に対する情熱」をしっかりと伝えられれば問題ないでしょう。
主専攻は「日本語教育に関する専門性」、副専攻は「教養の幅広さ」を中心に、自分をいかにアピールするかが重要です。
あとは、模擬授業を全力でやりきることが就職につながります。
Ⅱ 日本語教育以外の一般企業に就職する場合
.png)
日本語教育業界以外の一般企業に就職する場合もどちらかが有利・不利に働くことはありません。
大学で日本語教育を学んでも卒業後、全く違う業界に就職する人も少なくないでしょう。
残念ながら、日本語教育の分野は広く一般に認知されているとは言えません。
就職活動では主専攻・副専攻に関わらず、「大学で学んだ日本語教育の知識やスキルを就職後どう活かせるか」を面接官に強くアピールする必要があります。
また、副専攻であっても履歴書には必ず記載して身につけたスキルを書面上でも明らかにすることが重要です。
副専攻を履修すると、大学から正式な修了証が発行されます。
修了証は自分のスキルを対外的に証明できるものなのです。
Ⅲ 研究者をめざして大学院に進学する場合

研究者をめざして就職せずに直接大学院への進学をめざす場合、主専攻が有利に働きます。
なぜなら、大学院では大学と比べると、より専門性の高い研究成果が求められるから。
大学で主専攻することにより専門理論を高いレベルで習得できるはずです。
また、日本語教育に関するあらゆる分野の専門科目を数多く履修しているため、より多角的な視点から研究テーマにアプローチできる利点もあります。
将来研究者をめざすのであれば、日本語教育を主専攻したほうがよいでしょう。
ただし、副専攻だからといって大学院進学への道が閉ざされることは決してありません。
副専攻や養成講座修了後、現場経験を積んでから大学院へ進学し、研究者になる方も多くいます。
研究テーマが現場視点からのアプローチであれば、むしろ日本語教師としての現場経験が必須になります。
それだけ日本語教育の世界は広いということがいえるでしょう。
それでも迷ったら・・・

ここまで、主専攻と副専攻で日本語教師の資格を取得することの違いを解説してきましたが、それでもまだ迷ってしまう人のために、どちらがおすすめか整理してみました。
最終的に決めるのはあなた本人ですが、参考にしてください。
| 専攻 | おすすめの人 |
|---|---|
| 主専攻 | ・将来日本語教師になりたい人 ・最も興味がある学問領域が日本語教育の人 ・日本語教育の研究者になりたい人 ・日本語教育関係の会社に就職したい人 |
| 副専攻 | ・他にやりたいことがあり日本語教師になるか迷っている人 ・研究内容の一部として学びたい人 ・とりあえず資格を取っておきたい人 |
まとめ

以上、日本語教師の資格を大学で取ろうとするときに知っておくべき「主専攻と副専攻の違い」について解説してきました。
大学の専攻を「なんとなく」で選び、後悔してしまう人も多いと聞きます。
日本語教師に興味をもってこの記事を読んでいただいた方には、大学でどの分野を主専攻・副専攻とするか真剣に考え、後悔のない選択をしていただきたいと願っています。
当サイトのおすすめ日本語教師養成講座No.2
\ 口コミ評価 (4.5) /
ヒューマンアカデミー

<全国32校舎・業界最大手の安心感!>
<国家資格対応・日本語教員試験基礎試験免除>
<日本語教員試験合格率91.8%!>
<実習・サポートも充実! 就職率96.3%>
<リスキリング支援制度で最大70%還元>
<教育訓練給付金制度で最大50%おトクに!>
\ デジタルパンフレットを見てみる /
\ まずは気軽に相談、オンラインもOK/


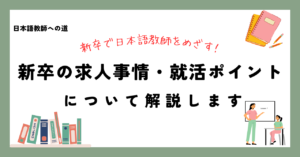
で取る方法-300x157.png)
